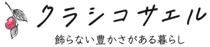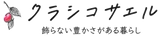行事「お正月」〜日付ごとの暮らしのアイデアと行事食のレシピ〜

\季節のささやきに、耳をすませて/ブログ「季節のささやき」では、季節の節句や行事ごとに、暮らしを豊かにするアイデアや旬の食材のレシピなどをお届けします。
|
1.お正月ってどんな行事?
|
1.お正月ってどんな行事?
∟ by.おべんとうつづり「手作りおせちの段取りとスケジュール」
お正月(おしょうがつ)は、年神様を迎えて新しい1年の始まりを祝う期間もしくはその期間に行われる行事のこと。
昔は、“正月”は1月すべてを指す別称だったそうですが、現在のお正月の期間は元日(がんじつ)から三が日まで、もしくは松の内(まつのうち)までとされるのが一般的です。
2.お正月の日づけごとの暮らしのアイデア
お正月やお正月に関連する日についてまとめ、日付けごとの暮らしのアイデアをご紹介します。
【松迎え(まつむかえ)】
始まり:関東など多くの地域12月13日、関西ほか一部12月8日
終わり:12月28日もしくは12月30日
∟ by.Tammy*「正月事始め:心穏やかに新年を迎えるための準備」
お正月に年神様を迎えるための準備を行う期間。
始まりの12月13日(もしくは8日)は鬼宿日(鬼が家にいるため邪魔されることがない吉日)で「正月事始め」とされ、同じく吉日とされる12月28日もしくは30日までに終わらせるのが理想的とされる。
✔︎ 松迎えその①:煤払いを始めとした大掃除
お掃除や整理整頓にまつわる記事はこちら↓
・ほうき時間のすすめ - by.りえ
・かごのお手入れ - by.なこ
・木製品のお手入れ - by.なこ
・すっきり心地よい冷蔵庫に - by.りえ
✔︎ 松迎えその②:お餅やおせちなどのお供物の準備
おせちについては、詳しくは 3.お正月の行事食のレシピ で。
おせちの中身は各家庭で様々ですが、早織さんが紹介された美しくとっても美味しそうな自家製からすみは時間も要するため、早めの取り掛かりが正解です…!
✔︎ 松迎えその③:お正月飾りを飾る
・お正月飾りの中で、また年神様を迎える準備の中でも特に重要とされていたのが縁起の良い松の木を使って作られた門松を飾ることであり、すなわち「松迎え」の由来となったそう。
| 門松:年神様が家にやってくるための目印。玄関に飾る。 しめ縄:年神様を迎えるために家を清め、守る役割。神棚に飾る。 鏡餅:年神様へのお供え物もしくは年神様の依代。神棚や床の間に飾る。 |
・お正月飾りを飾るのは12月28日もしくは12月30日が縁起が良い。(12月29日は“二重の苦”、12月31日は“一夜飾り”とされ避けた方が良いとされる。)
nijisuzumeさんは稲藁の素材にこだわらない、身近な自然素材を使った手作りのしめ縄の楽しみ方を伝えてくだっています。
kaeさんが紹介された干支のファブリックパネル作りも楽しそうです。
【大晦日(おおみそか)】12月31日
・1年の締めくくりであり、新年を清らかに迎えるための日。
・元々「晦日(みそか)」は毎月の最終日のことだった。(別名「つごもり」=月が隠れるの意)12月の最終日に特別に「大」を付けて「大晦日」となった。
・風習:大掃除をする、年越し蕎麦を食べる、除夜の鐘を聞く、など。
【元日(がんじつ)】1月1日
・新しい年の始まりの日。
・“始まり”や“最初”を意味する「元(がん)」に「日」をつなげて1年の始まりを意味する。
・一般的に元日は1月1日その日を、元旦(がんたん)は元日の朝を指す。
・風習:初日の出を見る、年賀状をこの日に届くように送る、など。
【三が日(さんがにち)】1月1日〜1月3日
・多くの企業や学校がお休みとなり、日本のお正月の中でも新年の祝いと共に家族や親しい人々と過ごす最も大切なお正月の期間。
・風習:初詣に行く、おせちやお屠蘇をいただく、お年玉を送る、など。
「普段使うものはお正月に新調すると良い一年になる」とのことで、平本麻美さんからはお箸などを新調されるお正月の験担ぎのアイデアも。
【松の内(まつのうち)】
始まり:1月1日
終わり:関東など多くの地域1月7日、関西ほか一部1月15日
・年神様を迎え、お正月のお祝いをする期間。年神様を迎えているこの期間が一般的に「お正月」とされる。
・風習:松の内の終わり(7日/15日)もしくはその翌日(8日/16日)に門松やしめ縄を片付ける。(片付けた門松やしめ縄は小正月前後に行われるどんど焼きで焚き上げる)(鏡餅は鏡開きの日に)
【人日(じんじつ)/七草(ななくさ)の節句】1月7日
・五節句のひとつ。
・風習:春の七草を入れた七草粥を食べる。
人日の節句の暮らしのアイデア、行事食などは季節のささやき:五節句「人日の節句」で。
【鏡開き】
関東など多くの地域1月11日、関西ほか一部1月15日
・松の内が終わり、奇数が並んで吉日とされた1月11日に、年神様にお供えしていた鏡餅を下げて食べる日。
・年神様の力を分けてもらい、無病息災や家内安全を願う意味がある。
鏡開きをしたお餅は、sonomiさんが紹介された手作りおかきにして楽しむアレンジはいかがでしょうか。
【小正月(こしょうがつ)】1月15日
・旧暦1月15日は新年最初の満月の日。昔は満月に五穀豊穣を願う農耕儀礼としての意味合いが強かったが、現在では賑やかな大正月を終え、落ち着いた心で新年の暮らしを整える日として大切にされている。
・風習:小豆粥を食べる、どんど焼き(お正月飾りを焚き上げる)
3.お正月の行事食とレシピ
お正月の行事食には、健康長寿、子孫繁栄や豊作を願う意味が込められた料理が多く、食べ物一つ一つに縁起を担ぐ伝統があります。
家庭や地域によって食べるものや意味合いは異なりますが、代表的なものには以下があります。
✔︎ おせち料理
主に健康長寿や子孫繁栄などの縁起を担いだ数種類の料理を重箱に詰めたお正月の行事食。
・黒豆:「豆」は健康長寿・子孫繁栄「黒」は厄除けや魔除け
・数の子:卵がたくさん入っているので子孫繁栄
・伊達巻:卵でできているため子孫繁栄、巻物に似ているため学業成就
・紅白かまぼこ:形や色で健康長寿・子孫繁栄・家庭円満
・昆布巻き:「よろこぶ」にかけて幸運、健康長寿
・栗きんとん:金運、豊かさ
・田作り/ごまめ:豊作
・れんこん:先の見通しが立つように
おせちにまつわる記事はこちら↓

おべんとうつづりさんの美しい手作りおせちの段取りとスケジュールの記事はこちらから。
年末を慌てず迎えるための日付けごとの進め方は必見です。
その他のおせちの記事はこちら↓
・お正月は「がんばらないお節」- by.川上琴美
・我が家のおせち - by.おべんとうつづり
・おせちにお弁当に!田作り - by.あさこ
・彩りてまり寿司と菊花かぶ - by.tome
・ハレの日の擬製豆腐 - by.えみ
✔︎ お雑煮
お餅やその他の具材を入れるお正月の汁物。地域によって味付けや具材が異なる。
・関東風:鶏肉や根菜を使った澄まし汁。お餅は角餅。
・関西風:白味噌仕立て。お餅は丸餅。
✔︎ 祝い肴(いわいざかな)
お正月に食べる海鮮類。
・鯛:「めでたい」にかけて幸運、健康長寿
・海老:腰が曲がった海老にかけて健康長寿
・鮭:子孫繁栄
✔︎ お屠蘇(おとそ)
元旦に飲む薬草入りのお酒。健康長寿を願って飲まれる。
平本麻美さんは自分好みの調合でお屠蘇を手作りするアイデアを紹介されています。一晩漬け込む工程があるため、元日から楽しみたい方は大晦日に作ってみるのはいかがでしょうか。
いかがでしたか。
季節の移ろいをそっと暮らしに取り入れながら、健やかに楽しく過ごせますよう。
|