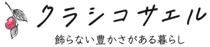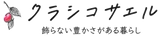人日の節句(七草の節句)〜いつ、どんな日?節句を楽しむアイデアと行事食のレシピ〜

\季節のささやきに、耳をすませて/ブログ「季節のささやき」では、季節の節句や行事ごとに、暮らしを豊かにするアイデアや旬の食材のレシピなどをお届けします。
|
1. 人日の節句っていつ?どんな日?
|
1. 人日の節句っていつ?どんな日?
毎年1月7日は五節句のひとつ“人日の節句(じんじつのせっく)”。
七草がゆを食べることが主な風習であるため、“七草の節句(ななくさのせっく)”とも呼ばれます。
昔の中国の風習では、お正月の最初の7日間を特定の生き物にちなんだ日として祝う日が定められていたそうです。
1日:鶏の日、2日:狗(犬)の日、3日:猪(豚)の日、4日:羊の日、5日:牛の日、6日:馬の日、7日:人の日…と、7日目が人の日=人日であり、人々の健康と幸せを願う行事が行われたのがこの節句の由来です。

【五節句(節句)】
五節句(節句)は「奇数は“陽”、偶数は“陰”。奇数同士を足して偶数になる日は“陽から転じて陰になりやすい”」という中国から伝わった考え方に由来し、奇数が重なり季節の節目でもある五節句のそれぞれの日に邪気を祓うという目的から始まったと言われる。
そのため、五節句の日には主に無病息災・豊作・子孫繁栄などを願って、その季節に合った植物や食べ物を神前にお供えし、邪気払いを行う。
このように、季節の“節”目となる日にお“供”えをする、という意味でもともとは「節供」と書かれていたが、漢字の表記の整理の中で約400年前頃から「節句」の表記に変化していった。
・1月7日:人日の節句(七草の節句)
・3月3日:上巳の節句(桃の節句)
・5月5日:端午の節句(菖蒲の節句)
・7月7日:七夕の節句(星まつり)
・9月9日:重陽の節句(菊の節句)
2. 人日の節句を楽しむアイデア
✔︎ “春の七草”を知る
“春の七草(はるのななくさ)”は、主に人日の節句に食べられる七草粥に用いられる七種類の野草。
冬の間に不足しがちな栄養を補い、無病息災や春の訪れを祈って食します。
・セリ(芹)
・ナズナ(薺):ペンペングサ
・ゴギョウ(御形):ハハコグサ
・ハコベラ(繁縷):ハコベ
・ホトケノザ(仏の座):コオニタビラコ(春の七草のホトケノザは一般的なホトケノザとは異なる)
・スズナ(菘):カブ
・スズシロ(蘿蔔):ダイコン
十五夜に楽しまれる“秋の七草”もあります。
詳しくは季節のささやき:行事「十五夜」で。
nijisuzumeさんの読みもの「フーチバのおはなし」では、一般的な春の七草に捉われず、身近な島の植物で春の七草を楽しむアイデアを紹介されています。
3. 人日の節句の行事食とそのレシピ

別名“七草の節句”とも呼ばれるように、七草粥が人日の節句の行事食となります。
tomeさんの読みもの「七草粥とアレンジ粥」では、七草をあと乗せする七草粥のレシピを紹介されています。アレンジ粥も美味しそう。
七草で冬の間に不足しがちな栄養を補い、無病息災や春の訪れを願いましょう。
行事食に願いをこめて、人日の節句を健やかに過ごせますよう。
|