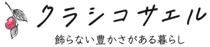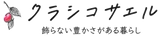【2025年】行事:十五夜(じゅうごや)〜十三夜、十日夜のことも〜

|
1. 十五夜っていつ?どんな日?(十三夜、十日夜のことも)
|
〜季節のささやきに、耳をすませて〜
ブログ「季節のささやき」では、季節の節句や行事ごとに、暮らしを豊かにするアイデアや旬の食材のレシピなどをお届けします。
1.十五夜っていつ?どんな日?(十三夜、十日夜のことも)
∟ by.なこ:お月見の手ぬぐい
2025年10月6日は1年でもっとも美しい月夜を楽しむ“十五夜(じゅうごや)”です。
お月見の行事は、実は十五夜を含めて年3回あります。
あとの2回は“十三夜(じゅうさんや)”と“十日夜(とおかんや/とおかや)”で、すべての日が晴れて月を見られることは、とても縁起が良いと言われています。
3つの月見を合わせて“三月見(みつきみ)”、十五夜と十三夜を合わせて“二夜の月(ふたよのつき)”とも呼ばれます。
【十五夜】2025年10月6日(月)
・旧暦8月15日の中秋に昇る1年でもっとも美しい月“中秋の名月”に、秋の豊作を祈願する。
(旧暦7〜9月は秋、その真ん中である8月15日が“中秋”と呼ばれていたため)
・お月見団子や実りの前の稲穂、もしくはすすきのほか、この時期に収穫を迎える里芋やさつまいもをお供えすることから“芋名月”とも呼ばれる。
【十三夜】2025年11月2日(日)
・旧暦9月13日に昇る中秋の名月に次いで美しい月に、秋の収穫を感謝する。
・十五夜の次にやってくることからこの月を“後の月(のちのつき)”とも呼ぶ。
・稲作の収穫を終える地域も多いため、お米の粉で作ったお月見団子のほか、この時期に収穫を迎える栗や豆などを供えることから“栗明月”“豆名月”とも呼ばれる。
【十日夜】2025年11月29日(土)
・稲刈りが終わる頃の旧暦10月10日に、田の神に今年の収穫に感謝し、来年の豊穣を祈願する。
・十五夜や十三夜と違ってお月見が主目的ではないため、満月に関係なく新暦の11月10日に行事を行う地域も多い。
2.十五夜を楽しむアイデア
▼ 十五夜にお供えする植物のこと
十五夜にお供えする植物としては、“ススキ”が有名です。
ススキは茎が中空であることから古くから神様の依代だと考えられていたこと、またススキの鋭い切り口が魔除けになると考えられていたことなどが、十五夜のお供えとして飾られるようになった理由だそう。
十五夜に飾るススキは1本、3本、5本など奇数で飾ると良いといわれています。
∟ by.なこ:ススキ、フジバカマ、満月のような菊
また、ススキは“秋の七草”のひとつでもあります。
秋の七草は萩(ハギ)、尾花(オバナ)=ススキ、葛(クズ)、撫子(ナデシコ)、女郎花(オミナエシ)、藤袴(フジバカマ)、桔梗(キキョウ)。
春の七草のように食べるのではなく、秋の訪れを感じられる花として鑑賞して楽しみます。
ハギは鉢植え、ススキ、クズは土手などにいることが多く、他のナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、キキョウは切り花としてお花屋さんで購入できるようです。
ススキ以外の揃えられる秋の七草も一緒に飾りながら中秋の名月を楽しむのも、より季節感があってすてきですね。
▼ 行事“十五夜”を楽しむ読みもの
・行事食:お月見団子 - by.平本麻美
・十五夜に楽しむフルーツ白玉 - by.ryuryu
・季節のお飾り〜十五夜のお月見〜 - by.なこ
・国産素材かぼちゃ餡の月見大福 - by.的場 シオリ
西表島在住のnijisuzumeさんは毎年 中秋の名月と、その次の満月の日に、真っ赤に色づいた月桃の実を収穫しているそうです。
3.十五夜の行事食(レシピ付き)
十五夜の行事食“はお月見団子”。
丸いお団子の意味合いは「家族円満」だとか。
また、子どもたちがお月見の供物を盗み食いすることを「お月様がお供え物を食べてくれた」として「月見どろぼう」「供物ぬすみ」「月見ぬすみ」などと言って歓迎する風習もあるそうです。
✔︎ お月見団子を三方に乗せて、より正式にお供えするなら ≫ こちらの記事
✔︎ お月見団子をフルーツ白玉にして、より気軽に、子どもたちも一緒に楽しめるようにするなら ≫ こちらの記事
いかがでしたか。
季節の移ろいをそっと暮らしに取り入れながら、健やかに過ごせますよう。
|