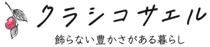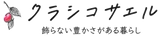上巳の節句(桃の節句)〜いつ、どんな日?節句を楽しむアイデアと行事食のレシピ〜

\季節のささやきに、耳をすませて/ブログ「季節のささやき」では、季節の節句や行事ごとに、暮らしを豊かにするアイデアや旬の食材のレシピなどをお届けします。
|
1. 上巳の節句っていつ?どんな日?
|
1. 上巳の節句っていつ?どんな日?
毎年3月3日は、五節句のひとつ“上巳の節句(じょうし/じょうみのせっく)”。
もともとは厄払いのための行事でしたが、現在は特に女の子の健やかな成長と健康を願う「桃の節句」や「ひな祭り」として親しまれています。
起源は古代中国にあり、旧暦では日付に十二支が割り当てられていたため、12日ごとに巡る「巳の日」のうち、3月最初の巳の日=上巳に川で身を清め、邪気を払う風習があったとされています。
この風習が日本にも伝わり、江戸時代には3月3日が正式な五節句のひとつに定められました。
江戸時代までの旧暦3月3日は現在の新暦では4月上旬頃。
ちょうど桃の花が咲く頃だったため「桃の節句」とも呼ばれています。
現在の新暦ではまだ桃の開花には早いため、本来の風習とは季節感に若干ずれが生じていますが、春を感じるお祝いとして大切に受け継がれています。

2. 上巳の節句を楽しむアイデア
▼ ひな飾りを飾る
✔︎ ひな人形
ひな飾りの代表、ひな人形は、もともと「ひとがた」と呼ばれる紙の人型が始まりとされています。
自身の穢れや災いを移し、身代わりとして川に流す厄払いの風習に使われていました。
やがてこの風習は、貴族の子どもたちの人形遊び「ひいなあそび」と結びつき、「流し雛」として受けつがれていきます。
現在でもその風習が残る地域が多くあります。
その後、人形作りの技術が発達するとともに、室町時代頃からは人形を飾る文化へと移り、現在のようにひな人形を家庭に飾る風習へと変化していきました。
kaeさんからは色合わせが楽しいはぎれで作るひな飾りのご提案です。
✔︎ 貝合わせ
平安時代から伝わる、対になる貝を探し当てる神経衰弱に似た遊びです。
ひな祭りの健やかな成長や幸せな結婚の願いとも重なり、夫婦円満や良縁を象徴するしつらえとしても親しまれてきました。
平本麻美さんは、そんな貝合わせを手作りするアイデアをご紹介されています。
3. 上巳の節句の行事食とそのレシピ
女の子と健やかな成長を願い、厄除けや長寿の意味合いをもった菱餅、ひなあられ、蛤やあさりなどの貝のお吸い物やちらし寿司、白酒(甘酒)が行事食として並ぶことが多いです。
平本麻美さんからは雛祭りにおすすめのご飯もののアイデア(下記画像↓)。
また、こちらの記事ではテーブルコーディネートのご提案も。
tomeさんからもご飯ものとして、春野菜と冬野菜で作るかわいいモザイクちらし寿司のレシピです。
おべんとうつづりさんからはこの時期のランチとしてご友人に用意されたお料理のご紹介です。
お飾りや行事食に願いをこめて、上巳の節句を健やかに過ごせますよう。
|