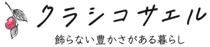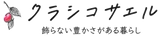かご編みのおはなし


連載:シチシチムジクイ 島の暮らし
西表島在住のクラシライター:nijisuzumeさん(Instagram)より、自然の移り変わりや植物のサイクルに合わせたものづくり〈シチシチムジクイ〉をお届けします。
✔︎ クバのかご編み
クバの葉で作るウブルという民具があります。ウブルは沖縄の方言で「水汲み」という意味で、クバの葉のウブルはクバの葉で作った水汲み桶。昔は井戸の水を汲むためのツルベとしてや、サバニ(昔の木の船)の船底に入り込んだ海水を汲み出すのにも用いられたそうです。
そんなウブルの作り方を教えてもらって、色々な形のものを作ってみたことがあるのですが、ひとつだけ私には引っかかってしまう点がありました。それは、綺麗で柔らかな若いクバの葉を、わざわざ採って来なければならないということ。

伸びゆく若芽を採ってしまうのではなくて、剪定することになる下の方の硬いクバの葉を用いて作ることはできないかと思って試してみましたが、さすがに葉が大きくて硬いので上手くいきませんでした。

では、剪定した下の方の硬いクバの葉の中心部分からはクバ扇を作り、残った細い葉の部分をうまく生かして作ることはできないかと思い、試しに編んでみると‥

ウブルに似た形のクバの葉のかごが編み上がりました。隙間があるからさすがに水汲みはできないけれど、かごとして使うのであればこちらでも良さそうです。お菓子などを載せても良さそうですが、私は食事の時や手仕事をする際に、おしぼりを載せて使おうと思っています。
ワークショップ
|
✔︎ アダンパのかご編み
道路の脇にアダンの葉が大きく生い茂っているのを朝散歩の時に見つけました。もっと大きくなって道からはみ出てしまうと、草刈り機で刈られてしまうので、その前に頂いてくることにしました。

刈ったアダンの葉は、トゲに気をつけながら細く裂き、湯がき、乾かしながら何度も鞣(なめ)します。鞣し終えてテープ状になったアダンの葉は、村の祭の時に履くアダンパ草履を編むのに使います。

こうして拵えたアダンパのテープは、草履にするだけではなく、かごを編むのにも使えます。月桃をテープ状にしたものでも同じようにかご編みができるのですが、月桃は乾燥するとパキパキと折れてしまって、慣れないと上手に編みにくいので、折れにくくて比較的編みやすいアダンパを使って、小さなものや大きなもの、背の高いものや低いもの、用途に合わせてかごを編むことが多いです。

眼鏡を入れるケースが欲しくて、蓋付きのかごを編んだり、ちょっとした持ち運べるペンケースが必要で、こちらも蓋付きで作ってみたり、編んだかごに磁石を入れ込んで冷蔵庫に貼り付けて、ペンやハサミを入れて使ったり、いつも必要なカタチのかごを自由に編んで作り、日々の暮らしの中で使っています。

ワークショップ
|
身近にある植物を素材として、必要なものを自分の手で編んで作ることができると、買ってくるのとは違って、ちょうど良い大きさに仕上げたり、用途に合ったものを作ったりすることができます。
暮らしに必要なものを自由に作り出して、日々の暮らしの中で役立てていけるのは豊かなことだと思います。日々の暮らしの中で「編む」という手技を用いることで、ものづくりの幅がさらに広がってゆきますように。
2月の読みもの2月の暮らしや行事を楽しむアイデアや旬の食べ物に関すること(レシピ付き記事も)、3月の準備などの記事をお楽しみください♪ |