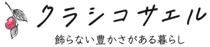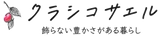金木犀ほうじ茶と栗ご飯

少しずつ陽が落ちるのが早くなり、風の中にやわらかな静けさを感じます。
そんな秋のはじまりに楽しみたいのは、ひと手間をかけた栗ご飯と、香りを味わう金木犀焙じ茶の組み合わせ。
火を止めた土鍋の余熱、グラスのなかでゆれる氷、香り立つお茶。
どれもが少しずつ、夏から秋へと移りゆく今だけの風景です。

忙しい日々の合間に、ひと手間かけたご飯とお茶を楽しむことで、心もゆっくりと季節に追いついていくような――
そんな9月の、小さなお茶時間をどうぞ。

栗を剥くという作業は、少し面倒にも感じられるけれど、その手間がむしろ、季節と向き合う大切な時間になります。
大きな栗をひとつひとつ剥いて、ほんの少しの旨塩でシンプルに炊き上げる栗ご飯は、炊きたての湯気の中にふわりと甘みが立ち上がり、口に含むとほろっと崩れて、滋味が広がる。
素材の力を信じて、秋の恵みをそのまま感じられるような、一杯です。
|
合わせたお茶は、自家製のドライ金木犀を使った金木犀ほうじ茶。
去年の秋に摘み、ゆっくりと乾かしておいた金木犀の花びらを香ばしいほうじ茶にブレンドしました。去年11月のコラムに金木犀のドライの仕方を載せています。
南部鉄器の白い急須に、ほうじ茶の茶葉と金木犀を入れて熱湯を注ぎ、香りが立つまでしばらく蒸らします。
茶をガラスの片口に移して氷で冷やし、金木犀の花びらを浮かべたグラスにそっと注ぐと、目にも涼やかで、夏から秋への移り変わりを感じる風情の一杯に。
|
ほうじ茶の香ばしさの奥から、ほのかに甘くやさしい金木犀がふわりと香り、まるで秋そのものを飲んでいるような余韻を残します。

土鍋は長谷園のかまどさん2合炊き、
ご飯椀は愛知県の杉江善次さんの器
忙しい日々の合間に、ひと手間かけたご飯とお茶を楽しむことで、心もゆっくりと季節に追いついていくような――
どちらも、今だけの季節の恵みを静かに楽しませてくれる存在です。
そんな9月の小さな秋を味わう、静かな時間をどうぞ。
#お茶を楽しむ / #ほうじ茶/焙じ茶 / #栗(9〜10月)/ #炊き込みごはんのレシピ
9月の読みもの9月の暮らしや行事を楽しむアイデアや旬の食べ物に関すること(レシピ付き記事も)、10月の準備などの記事をお楽しみください♪ |