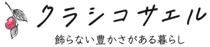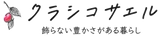必要なものを自分の手でつくる(生活雑貨編)


連載:シチシチムジクイ 島の暮らし
西表島在住のクラシライター:nijisuzumeさん(Instagram)より、自然の移り変わりや植物のサイクルに合わせたものづくり〈シチシチムジクイ〉をお届けします。
二十数年前の島に移住したての頃、必要なものを自分の手でつくる暮らしが、まだまだ島に色濃く残っていました。
それぞれの家に田んぼがあり、お米はユイマールでみんなで協力して手植え手刈りで作っていましたし、普段食べる野菜は畑で、薬味などは家の周辺の小さなスペースで、お茶は近くに生えている野草や薬草を乾燥させて作っていました。
おばあやおじいの家にお邪魔すると、ガンシナーと呼ばれる鍋敷きや、アンツクという編みカゴ、稲藁で拵えたほうき、チガヤを編んだシンメー鍋の蓋、団扇がわりのクバ扇、竹で編まれたバーキというかご、ピーデで編んだ脱衣カゴなど、身の回りの生活の道具の多くが、自分たちの手で作られたものでした。
そんなおじいとおばあから、「身の回りの植物で、自分の暮らしに必要なものを、自分の手でつくる」ことを教えてもらった私は、必要なものがあった時に、すぐに買って済ますのではなく、身近な植物などを使って可能な限り自分の手で作ろうとするようになりました。
前回は身の回りの植物などを用いて作ったバッグ類を紹介しました。今回は身近な植物を材料にして作った生活雑貨を紹介しようと思います。「必要なものを自分の手でつくる」時のヒントとなれば幸いです。
✔︎ セイバンモロコシの箒

県道沿いや空き地、我が家の裏道にもびっしりと生えているセイバンモロコシ。道の草刈りのたびに伐採するのですが、南国の温暖な気候ゆえ、一年を通して刈っても刈ってもすぐに生えてきてしまいます。そのセイバンモロコシの穂の部分を取ってつくる箒。しなやかで使い勝手が良いので、何本も作っておいて、机の上、窓のサッシ、下駄箱などそれぞれの場所に置いて使い分け、傷んだら畑の土に還しています。
✔︎ クバの団扇

クバの葉を切り取ってつくるクバ扇(クバオージ)と呼ばれるクバの葉の団扇。クバの葉の下葉を剪定した際には捨てずに取っておき、梅雨が明けて晴天続きになる時期に、雨戸の下敷きにして平べったく乾かしてつくっています。クバの若い葉でなく下の葉で作っており、硬くて丈夫なので、BBQの炭を起こすときや、たき火をする時にも重宝しています。
✔︎ アダンパの眼鏡ケース

鋭い棘を持つアダンの葉は、道沿いで生い茂ると通行の際に棘でケガをしてしまうこともあるので、大きくなったものは定期的に伐採されます。そのアダンの葉をテープ状に拵えて編むと、さまざまな形のカゴとなるので、こちらのアダンの葉で眼鏡ケースを作って愛用しています。軽いのにクッション性があって中の眼鏡を守ってくれるので、旅行の時などにはこちらの眼鏡ケースに入れて持ち歩いています。
✔︎ 月桃の茶漉し

島のあらゆるところで見られる月桃は、葉はお餅を包んで蒸したりする時に、実はお茶に、茎はかごを編んだりと、様々な用途で用いられています。その月桃の茎で茶漉しを作り、日々のお茶を淹れる際に使用しています。金属の茶漉しが苦手だったので、植物で作られたこの月桃の茶漉しを気に入って重宝しています。
かつての島の暮らしのように、というまでには至らないけれど、必要なものがあった時に、すぐに買って済まそうとするのではなく、自分の手で作れないかどうか考えてみて、できる限り「身の回りの植物で、自分の暮らしに必要なものを、自分の手でつくる」暮らしができたらいいなと思っています。
7月の読みもの7月の暮らしや行事を楽しむアイデアや旬の食べ物に関すること(レシピ付き記事も)、8月の準備などの記事をお楽しみください♪ |