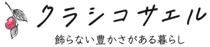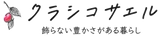八重山諸島のひとつ、西表島在住で、日曜日の連載「シチシチムジクイ島の暮らし」を書いてくださっている虹雀nijisuzumeさんを講師に迎え、ワークショップを開催します。
今回は、月桃の三角茶漉しを手作りするワークショップ。
特製の碧い月桃茶も一緒愉しんでいただきます。
20年ほど前に島へ移住され、島の人たちや自然とともに暮らしを楽しんでいる様子が人気で、細部まで宿る無駄のない丁寧な手仕事からは、人柄が垣間見えます。
nijisuzumeさんが語る言葉や手の動きを間近で見て、ただ技を学ぶのではなく、その背景にある自然への敬意や、無駄にしない知恵をも学ぶワークショップ。
手仕事に使う植物の感触、静かに流れる時間ーー都会の中でそこだけが島の空気に包まれたような場所になり、ワークショップを受講された方はまるで西表島にワープしたような感覚になるかもしれません。

以下nijisuzumeさんより▼
長い間ずっと、身近な植物素材で茶漉しをつくりたいと考えていました。というのも、淹れたお茶に金属イオンが移ってしまいそうで、金属の茶漉しが苦手だったからです。
そんなある日、石垣島のアジア雑貨屋さんでふと植物で編まれた子どもの笠が目に留まりました。この形状を応用したら茶漉しになるかもと閃き、買って帰ってじっくり観察しながら研究し、素材や編み方、縁の仕上げ方を変えて試行錯誤を重ね、そうして完成したのがこちらの月桃を素材にした三角茶漉しです。

「月桃」というお茶にもなる植物を用いて製作するため安心して使用できますし、その三角という形状ゆえに、小さなティーカップ、マグカップ、大きなポットまで、様々な器に合わせることができるのも良さです。
また、全て自然素材で作られているため、いつか役目を終えた際には、土に還すことができます。
✔︎ ワークショップ詳細
お茶に、料理に、香りのものに、かご編みに、化粧水にと、様々な用途で用いられる月桃という植物。沖縄ではポピュラーなこちらの月桃という植物について、その採取の仕方と拵え方、心に留めておくと良いことなどについてお伝えし、月桃という植物についての理解を深めた上で製作に入ります。
今回のワークショップでは、碧い月桃茶を愉しみながら、月桃の茎を編んで三角茶漉しを作ります。

立体的な三角に編むという作業は、かご編み初心者には少々難しいと感じられるかもしれませんが、実はこの三角茶漉しに限っては、多少編むのが苦手な方が良いのです。というのもキッチリと上手に詰めて編んでしまうと、お茶を漉しづらくなってしまうため、隙間を開けて編む必要があるからです。
月桃の特性上、折れやすくて編みにくいという点がありますが、折れずに編み終えるコツをお伝えしながら、最後まで仕上げられるようにお手伝いします。

ワークショップで作った月桃の三角茶漉しはお持ち帰りいただき、緑茶、さんぴん茶、紅茶、ハーブティーなど、お好きなお茶の茶漉しとしてお使いいただけます。また茶漉しは、きれいに洗って乾燥させれば、何度でも繰り返し使えます。心を込めて自分の手で作った月桃の三角茶漉しを、ぜひ日々の暮らしの道具として傍に置いて下さい。
島に移住して20数年、村のおじいやおばあからたくさんのことを学びました。そうして受け継いだ知恵や手技、そこから着想を得て広がった手技を、少しずつ大切に伝えたいと思っています。
植物を採る際には「こちらの植物を採らせてください決して無駄にはしません」と手を合わせて採らせてもらっています。「大切なものは目には見えない」その目に見えないものこそが大切なのだということを知る人に、繋げていきたいと願っています。
自然との調和の中にある手仕事を通じ、その向こう側にある自然と繋がりながら、すぐ隣に手仕事がある暮らし、必要なものや欲しいものを自分の手でつくれる暮らし。そんな暮らしが広がりますように。
✔︎ 製作する月桃の三角茶漉しについて
【サイズ】
一辺 約13cm
高さ 約6cm
【注意事項】
*自然素材であるため、濡れた状態で放置するとカビが生えるおそれがありますので、使用後はしっかりと乾燥させ、風通しの良い場所で保管して下さい。
|
|
講師プロフィール
nijisuzume何にも無いけど、何でもある。沖縄の離島西表島にて、南の島の自然の恵みを大切にしながら、自然の移り変わりや植物のサイクルに合わせたものづくり〈シチシチムジクイ〉をしながら暮らしています。 |
\ CHECKED ITEM /