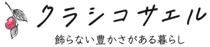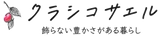天然素材の布のおはなし


連載:シチシチムジクイ 島の暮らし
西表島在住のクラシライター:nijisuzumeさん(Instagram)より、自然の移り変わりや植物のサイクルに合わせたものづくり〈シチシチムジクイ〉をお届けします。
普段は島暮らしの私ですが、年に数回は神奈川の実家に帰省し、中学卒業とともに親元を離れて島立ちした(島には高校がないのです)、三人の子ども達と久しぶりに会ったり、両親に元気な顔を見せたりしています。
そんな帰省の際に、密かに楽しみにしていることがあります。それは、骨董市巡り。前回の春の帰省も、今回の夏の帰省も、東京フォーラムで開催される江戸骨董市の時期と重なり、足を運ぶことができました。

骨董市が大好きな私、もちろん骨董の器も気になるのでひと通り見たりはするのですが、実は一番のお目当ては古い着物なのです。
古い昔の着物は、工業的な大量生産ではなく、昔ながらの手法で織られたものが多く、採るところから織り上げるところまでに多くの手間と時間をかけた、綿・麻・葛・大麻など植物繊維の自然布であったり、蚕の繭を綿状にした真綿を紡いで織られた紬などの絹織物であったりします。
また、化学染料の発達する以前の古い着物の多くは、藍染をはじめとする草木染めが施されていることが多いのです。
そんな手間暇をかけられた貴重な布は、現代であったらきっと手の届かないくらい高価であることでしょう。
けれどもそんな手間暇をかけられた天然素材で織られた布が、古い着物としてであるならば、手の届く価格で手に入れることができるのです。

骨董市にて迎えたこちらの古い着物は、絣模様の藍染の麻着物です。着物の内側の麻布にも、天然の藍染が施されています。

古いとはいえ比較的状態が良いので、着物を解かず、そのままの形を生かして、島の伝統的衣装であるスディナに仕立てようかなと考えています。

こちらは、染めを施していない生成りの古い麻の着物。大麻布のようです。しっかりとした麻の繊維で織られており、肌に触れるとサラッと涼しげ、かつ丈夫な生地なので、丁寧に解いて洗濯をした後は、ノースリーブシャツと夏用のパンツに仕立てようかなと思っています。

薄く藍染が施されたこちらの布は、蚕の繭を綿状にして紡いで織られた紬の着物を解いたもの。真綿を紡いで織っているため、触れると自然布と比べてあたたかな感触がします。こちらは絹布の保温性を生かして何らかの形の服に作り変えたいなと考えています。

島の暮らしの中で、苧麻や糸芭蕉から絲を採ったり、蚕を育てて繭から絹糸をずり出ししたりという経験をしたおかげなのでしょうか。自然の素材にたくさん触れるということにより、ふと気がつくと、骨董市で山積みとなって置かれている数々の古い着物の中からであっても、良き天然素材の着物を見つけ出せるようになってきたようです。
そして思うのです。こんなに素晴らしい天然の素材が古い着物として残るこの日本。しかも着物というものは、先人の素晴らしい知恵により最低限の裁断で作られており、解くと元の反物の形に近いものとなります。新たに布を織ることも、もちろん素敵なことですが、今ここにある古い着物としての布を生かすことができたならば、どんなに良いだろうかと。時を経て こうして残された古い着物たちを、生かせる手技を持った自分でありたいなと思います。
7月の読みもの7月の暮らしや行事を楽しむアイデアや旬の食べ物に関すること(レシピ付き記事も)、8月の準備などの記事をお楽しみください♪ |