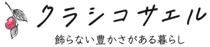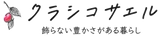自家製砂糖づくりの冬


連載:里山暮らし日々是好日
クラシライター:中里早紀子さん(Instagram)が自然や季節とともに移ろう田舎での里山暮らしの中で見つけたものたちをお届けします。
2025年がスタートして約半月。皆さまいかがお過ごしですか。寒の入りをして大寒を迎え、高知でも雪が降る寒さとなる日も多くあります。
✔︎ 砂糖にも“旬”がある⁉︎
今回は「砂糖」のお話。皆さんは普段どんな砂糖を使っていますか?
そして砂糖にも旬があることをご存知ですか?正確には「サトウキビ」の旬といったところでしょうか。
何でも作ってみたい中里家では2年前からサトウキビを栽培していて、それを冬に収穫し製糖、1年分の砂糖を自給しています。といっても栽培1年目は栽培量も収穫も少なく年間を通しての自給とはいきませんでした。
この冬は約45kgの砂糖が出来上がり、恐らく1年分を賄えるのでは?と淡い期待を寄せています。
ひとくちに「約45kg」と言ってもそれが出来上がるまでにはどんな道のりがあるのか?今回はそんなことを紐解いていきたいと思います。
✔︎ サトウキビの栽培について
簡単に説明すると、2月中旬頃に前年に育ったサトウキビの茎の節を土の中に埋め、3月中旬以降にそこから育った芽を畑に植え替え、今年の苗を育てていきます。前年に育ったサトウキビの根茎が残っていれば春には新たにそこから芽が出て苗へと育ちます。
ぐんぐんとまっすぐに苗は伸びて育ち、茎が太り夏には背丈を越えるほどになります。ざわわざわわと。この茎の部分に果汁が含まれるという訳です。
(厳密にはもっと細かい栽培作業がありますが、今回は割愛します)

収穫は冬。土の上に出ている茎の部分を刈り取っていきます。葉っぱも茂っていますがそれは取り除き、茎だけの状態にします。2mを優に超えるサトウキビですが、上の部分は熟成が進んでいないため、切り落とします。ちょっとのことですが、これで味が全然違うとのこと。

プロが作ったものはやっぱり全然違いますね。シュッと真っ直ぐなものはサトウキビ農家さんのもの。ぐにゃんと曲がっているのは中里家...。これも個性ということで...。

✔︎ いよいよ製糖!
まだ夜明け前。まず、サトウキビを機械にかけ搾汁していきます。約480kgあったサトウキビも、搾汁して残る果汁はおおよそ半分の240リットル。搾りかすは粉砕され、これはまた畑へ戻します。無駄なものは一切ありません。

絞った果汁は釜炊きへ。1番釜、すまし桶、2番釜、3番釜と順を経て炊いていき、水分を蒸発させながら糖度を上げていきます。1番釜ではアクが出てくるので何度も何度も丁寧にすくい上げる工程があります。もちろんですが、サトウキビの性質によって、ここでのアクの色や量といった具合も全く違うものになります。

1番釜からすまし桶へ入れて少し落ち着かせ、次は2番釜へ。ここからはひたすらに炊いていきます。釜の中の様子を見ながら、火の加減、混ぜ具合、アクの状態、前後の釜の進捗、全てに神経をめぐらせ進めていきます。朝日に照らされながら湯気がもくもくと上がる作業場の雰囲気は、何とも言えない美しさがあります。

最後の釜は仕上げの釜。糖度をはかり、まだ液体である砂糖の具合を確認し、ここぞ!というタイミングで釜からあげます。

仕上がった砂糖は攪拌しながらゆっくりと冷まし、こちらも絶妙なタイミングで型へと流し入れていき、固まれば砂糖の完成です。


できあがった砂糖はシャリシャリとした食感が特徴で、口の中にじんわり広がる優しい甘さが何ともいえず美味しいのです。ひとかけ、ひとかけ大切に食べたい、そんな気持ちです。

砂糖も野菜も同じです。作り手によって味も違うし、毎年変化がある。いつ食べても同じという均一に作られる工業技術は素晴らしいと思いますが、本来食べるもの(素材)とは変動があっていいものだと思います。それは味わう楽しみでもあるのですから。
そんなことを考えながら、2025年分の砂糖作り、無事に完結となりました。
そして、また来年はどんな砂糖になるでしょうか。冬の製糖を終え春への植え付けと続いていく、昔から続く季節の営みがここにはあります。
*
高知県内には製糖組合というのが数カ所あり、サトウキビ栽培、製糖が行われています。製糖は自分たちだけではできないので、この製糖組合さんにお邪魔し、教えていただき助けていただきながら作業をしています。組合の皆さま、本当にありがとうございます。
1月の読みもの1月の暮らしや行事を楽しむアイデアや旬の食べ物に関すること(レシピ付き記事も)、2月の準備などの記事をお楽しみください♪ |