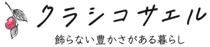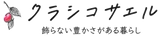あたたかい生成りのような色、どんぐり染め


連載:くらしの図工室byゆずの木アトリエ
日々のごはんを作るように、暮らしのものを作ったり、直したり。クラシライター:真鍋百萌さんより、「自然のものから暮らしのもの作り」のアイデアをお届けします。
暑かった夏が終わりに近づき、ようやく心地よい秋風が吹くようになりました。
私の住む東京都国分寺市には、あちらこちらに栗の農園があります。
この時期のお楽しみは、直売所に並ぶ栗です。
ツヤツヤ採れたての栗が買えるのは、ここに住んでいる特権だなぁと思います。
これから涼しくなって、美味しいものやお出かけが楽しい季節がやってきます。
そして、私にとっては秋から冬は手仕事シーズン!
自然の恵みをたくさんいただいて、庭に出て染色や木工、リース作り、服作り、ハーブを収穫したり、庭のリフォームと、やりたいことが目白押しです。
さて10月は、ベストシーズンのくぬぎのどんぐりを使って、あたたかな生成り色を染める方法をご紹介します。

∟ 自作の帽子、リネンスカート、綿ハンカチを染めました
雑木林に行かなくても、街中の公園でも、どんぐりは意外とたくさん拾えたりします。
くぬぎのどんぐりは染液がよく取れるので、染色にとてもおすすめです。
実は丸くて、カクト(どんぐりの帽子)はもじゃもじゃ。
葉は長くギザギザしています。
探してみてください。
|
自然からいただく色は、うつろいやすく、そのままでは布に定着しません。
媒染という作業が必要です。
染めてからも、日差しによって退色しますし、色移りもあるかもしれません。
既製品のように、ムラなく染めるのもコツが要ります。
それでも、使ううちに変化して馴染んでいき、使う人だけの唯一の表情になっていくのが、植物染めの一番の魅力だなぁと思います。
あたたかな生成りのような色に染めてみてはいかがでしょう。
10月の読みもの10月の暮らしや行事を楽しむアイデアや旬の食べ物に関すること(レシピ付き記事も)、11月の準備などの記事をお楽しみください♪ |